
犬が嘔吐する原因とは?色別に考えられる理由や病院に行くべき症状を解説
愛犬が突然黄色い液体や白い泡、ピンク色の血が混じった液体などを吐いたとき「何が原因?」「病院に行くべき?」と心配になる飼い主さんも多いでしょう。
本記事では、犬の嘔吐物の色やものによって、どんな原因が考えられるのかを紹介します。
また、病院に行くべき症状や吐いたときの対応についても解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
目次[非表示]
- 1.犬が吐いたときは嘔吐物の色やものを確認!
- 2.犬が吐いたときに病院に行くべき症状
- 2.1.嘔吐を繰り返す場合
- 2.2.なかなか吐き出せない場合
- 2.3.同時に下痢や血便もしている場合
- 2.4.震えている場合
- 3.犬の嘔吐で考えられる原因
- 4.犬が嘔吐したときはどうしたらいい?
- 4.1.犬が吐いた後の食事や水分補給
- 4.2.受診の際の持ち物
- 5.犬が嘔吐したら獣医師にオンライン相談をしよう
- 6.犬が嘔吐したら愛犬の様子を観察しよう
犬が吐いたときは嘔吐物の色やものを確認!

犬が嘔吐する原因は、自然現象や病的なものまでさまざま。
そのため、犬が吐いたときは、嘔吐物の色やものを確認することが原因の判断材料の1つとなります。愛犬がどんな色の何を吐いたのかを確認し、状況によって獣医師に相談してみましょう。
黄色い液体を吐いた
犬が黄色い液体を嘔吐した場合、胆汁を吐いてしまう「胆汁嘔吐症候群」の原因が考えられます。
胆汁嘔吐症候群とは、長時間胃のなかが空っぽになると、胆汁が逆流してしまう症状です。
そのため、早朝や夕方など空腹時によく見られるのも特徴。黄色い液体を吐いたら、空腹の時間が長いことが考えられるため、食事量や時間を調整するようにしましょう。
また、黄色い液体を繰り返し吐いたり、量が増えたりしてきたら、早めに獣医師に相談するのがおすすめです。
茶色い液体を吐いた
犬が茶色い液体を嘔吐した場合は、ドッグフードがうまく消化されていないことが考えられます。ドロドロした茶色い液体からドッグフードの匂いがすれば、それほど心配ない場合が多いです。
ただし、サラサラの茶色い液体の場合は、胃腸から出血し、血液が酸化していることも考えられます。判断が難しい場合は、吐いたものを持って病院で見てもらうのがよいでしょう。
現物があることで未消化による嘔吐なのか、胃や腸からの出血なのかを判断してもらえます。
白い泡を吐いた
犬が白い泡を吐いた場合、車酔いや緊張状態、空腹によって吐き気を感じていることが考えられます。白い泡を吐くときは、唾液が過剰に出て、それを飲み込むことによって引き起こされる場合が多いためです。
空腹時での嘔吐が考えられる場合は、食事の量や時間を調整してあげてください。また、車酔いが考えられる場合は、こまめに休憩をいれたり、ゆるやかな運転を心がけたり、動物病院で犬用の酔い止めを処方してもらったりするようにしましょう。
また、緊張での嘔吐が考えられる場合は、愛犬が落ち着く環境を作ってあげることが大切です。住み慣れたベッドやクレートなどを用意し、緊張や興奮などが起きないように工夫してあげましょう。
透明な液体を吐いた
透明な液体を吐いたときは、水や唾液、胃液などの吐き戻しが考えられます。水や唾液を吐き戻す原因は、勢いよく水を飲んだ際に起こりやすいです。そのため、愛犬が一気に水を飲まないように、飼い主さんが様子を見ながら水分補給させてあげてください。
また、胃液を吐くことは前述で解説した通り、空腹が原因であることが多いです。そのため、食事の回数や時間を調節してあげましょう。
ピンクや赤い液体を吐いた
ピンクや赤い液体を嘔吐した場合は、出血の可能性が考えられるため、早めに動物病院を受診するのがよいでしょう。
ピンクや赤い液体は、口腔内や食道、呼吸器、胃、腸などからの出血が考えられます。
明らかにおもちゃや尖ったものなどを噛んで口のなかから出血している場合は、それほど心配ありませんが、胃潰瘍や消化器官の腫瘍などで鮮血や黒い液体を吐くこともあります。このような場合は、早めに病院に受診するようにしましょう。
毛玉を吐いた
犬が毛玉を吐いたときは、抜けた被毛やほこりを飲み込んでしまった原因が考えられます。
被毛が抜けやすい換毛期は、とくに飲み込んでしまうことも多いです。愛犬に元気があるようなら、それほど心配せずに様子を見てあげましょう。
毛玉を吐く予防策は、こまめにブラッシングをしたり、掃除機をかけたりすることです。被毛やほこりなどをなるべく飲み込まないように清潔を心がけてあげましょう。
異物が混じっていた
犬の嘔吐物に異物が混じっていた場合は、速やかに病院に連れていくことが大切。おもちゃの破片や、アクセサリーなど食べてはいけないものを誤飲、誤食してしまうと、中毒症状や腸閉塞を起こす可能性があります。
誤飲や誤食は命の危険性もあるため、誤飲や誤食が疑われる場合は、気づいた時点で病院へ向かい、速やかに検査を受けてください。
犬が吐いたときに病院に行くべき症状

犬の嘔吐物や様子を確認しても、緊急性があるのかどうか飼い主で判断するのは難しいものです。
そこで、犬が吐いたときに病院に連れていくべき症状について紹介します。個人での判断が難しい場合は、オンライン相談を活用し、受診の判断をしてもらうのも1つの手段です。
嘔吐を繰り返す場合
犬が何度も嘔吐、毎日吐くことを繰り返す場合は、早く動物病院で診てもらうのがよいでしょう。繰り返し吐く場合は、消化器疾患や内臓疾患などさまざまな病気が疑われます。
食欲も元気もある場合でも、食事が愛犬に合っていない場合も考えられるため、原因を早く見つけてあげるためにも一度検査してもらうのがおすすめです。
なかなか吐き出せない場合
犬が何かを吐こうとしているのに、なかなか吐き出せない場合も早めに病院で診てもらうのがおすすめ。吐き出せない症状で考えられるのは、胃拡張や胃捻転症候群です。
胃拡張は、胃が拡張し、ねじれ(捻転)が生じることで発生します。胃や周囲の血流が遮断されてしまい、ショック状態に陥るケースもあるので、緊急性が高い病気です。苦しそうな様子やお腹が膨らんでいるといった症状が見られる場合は、すぐに獣医師に診てもらいましょう。
同時に下痢や血便もしている場合
犬が嘔吐と同時に、下痢や血便もしている場合は速やかに病院を受診しましょう。原因を特定して、早く症状を改善するためにも早めに診断を受けることが大切です。
犬が嘔吐と同時に下痢をする場合は、ストレスや消化不良、アレルギー、ウイルスなどさまざまな原因が考えられます。
とくに血便も同時に起る場合は、出血性胃腸炎の可能性もあるので注意しましょう。嘔吐と同時に、赤い液体、ゼリー状の赤い血便などが見られる場合は、すぐに獣医師の診察を受けましょう。
震えている場合
犬が嘔吐以外にも、少しでも震えている場合もすぐに病院で診察を受けるのがよいでしょう。嘔吐や震えの原因には、異物の誤飲や消化器官の病気、感染症などさまざまな原因が考えられるためです。
犬が震える理由は、寒さや傷み、恐怖心やストレスなどさまざまな理由があります。愛犬が元気があるか、発熱がないか、食欲はあるのかなど細かい部分も観察し、主治医に愛犬の様子を明確に伝えられるようにしましょう。
犬の嘔吐で考えられる原因

犬の嘔吐で考えられる原因は、以下の通りです。
- 空腹
- 緊張、興奮
- 車酔い
- 誤飲、誤食
- 消化器系の炎症、腫瘍、閉塞
- 中毒症状
- 感染症
- 肺や気管支などの呼吸器の出血
- 胃拡張、捻転症候群
上記の通り、犬は空腹による嘔吐や、病気による嘔吐などさまざまな原因で嘔吐します。犬が嘔吐する原因を判断する際は、嘔吐物の色やもの、そのほかに症状がないかなどを確認することが大切です。
とくに誤飲、誤食、消化器系の病気や中毒症状などは緊急性が高くなります。元気があるかないか、ご飯は食べているかなども観察し、いつもと違う様子が違う場合は、早めに動物病院を受診するのがよいでしょう。
犬が嘔吐したときはどうしたらいい?

犬が吐いたとき「食事や水分を与えてもいい?」「受診の際の持ち物は?」と心配な点が多いでしょう。
ここからは、犬が吐いたときの食事や水分補給、受診の際の持ち物について解説します。
犬が吐いた後の食事や水分補給
また、水や食べ物は一定期間与えないようにするのがよいでしょう。嘔吐の原因にもよりますが、吐いた直後に食事や水を胃に入れると、繰り返し吐いてしまい、さらに脱水が進行してしまう恐れがあります。
目安としては、半日から1日程度は食事や水分を与えず様子をみてあげてください。また、喉の乾きを訴えるようであれば、少量のお水や氷をゆっくりと与えるようにしましょう。
食事を与える場合は、ドライフードに水分を加えて、消化しやすくしてあげるのもおすすめ。3~4日かけて徐々に普段の食事に戻していきましょう。
ただし、嘔吐の原因が空腹だと考えられる場合は、絶食や絶水の必要はなく、いつも通りの食事や水を与えてOKです。
受診の際の持ち物
犬が嘔吐した際の病院への持ち物は、以下の通りです。
- 嘔吐物の写真
- ビニール袋や容器に入れた嘔吐物や排泄物
- 保険証や診察券
- 嘔吐してしまった場合の袋やティッシュ等
犬が吐いたときは、嘔吐物の写真や現物を持参しましょう。嘔吐物は時間が経つと色が変わってしまったりするため、吐いた直後の写真を残しておくと診断の際に役立ちます。
明らかに元気がない、繰り返し吐く、ほかの症状があるなどの場合は、速やかに病院に受診するのがおすすめ。受診の際は嘔吐物の写真やビニール袋や容器に入れた嘔吐物を持参し、以下の質問に応えられるように準備しておきましょう。
- いつから嘔吐しているのか
- 嘔吐の頻度
- ほかに症状はないか
- 元気や食欲があるか
- 誤飲や誤食などの可能性はないか
犬が嘔吐したら獣医師にオンライン相談をしよう
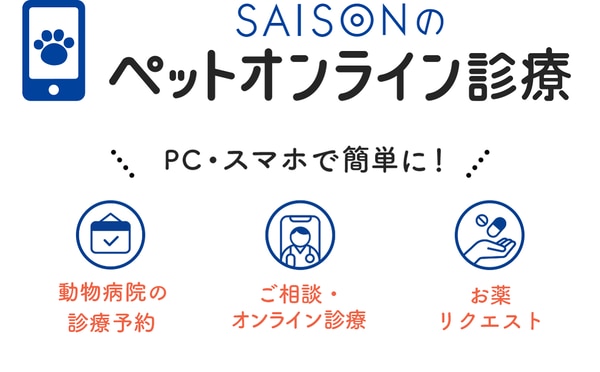
SAISONのペットオンライン診療は、獣医師にオンライン相談できるサービス。犬の嘔吐や下痢など気になる症状のお悩み相談にも対応しており「動物行動学」の観点から、なぜそのような行動をとるのか要因を分析して、改善に取り組む診療方法を提案します。
【以下のようなお悩みに対応】
・犬が嘔吐した
・ほかにも気になる症状がある
・元気はあるけど病院に連れていくべき?
・嘔吐を繰り返す
まずは、愛犬がどのような状態なのかしっかりカウンセリングを行い、プランを一緒に検討できるのもポイント。動物病院へ通院するかをオンラインで事前に判断してもらえるので、犬にストレスもかけずに診察を受けることが可能です。
※オンライン診療には、システム利用料280円(税込)が利用都度かかります。会員登録料は無料です。
犬が嘔吐したら愛犬の様子を観察しよう

愛犬が嘔吐したときは、嘔吐した液体の色やものを確認することで、原因の判断材料になります。
ただし、繰り返し吐いたり、ほかの症状があったり、元気がなかったりする場合は、自己判断せず獣医師に相談することが大切です。
受診の際には、いつから吐いているのか、頻度や回数、ほかに症状があるかなどを正確に伝える必要があるため、吐いた後は愛犬の様子をよく観察してあげましょう。

