
犬の下痢の原因とは?繰り返す際の食事や生活などの対処法も解説
犬の下痢は、食事やストレス、感染症などさまざまな原因が考えられます。また、下痢にもゼリー状や泥状などの形状が違うものがあるため、事前に把握しておくと獣医師の診断の際に役立つでしょう。
本記事では、犬が下痢をする原因や、症状や年齢別の対処法について解説。犬が下痢をしたときに「食事や散歩はどうする?」「受診の際には何が必要?」などといった気になる質問と回答も紹介しているので、参考にしてみてください。
目次[非表示]
- 1.犬が下痢する原因とは?
- 1.1.食事が原因の下痢
- 1.2.誤飲/誤食が原因の下痢
- 1.3.ストレスが原因の下痢
- 1.4.感染症が原因の下痢
- 1.5.寄生虫が原因の下痢
- 2.下痢の形状もチェック
- 3.犬の下痢の対処法とは?
- 3.1.元気で食欲ありの場合
- 3.2.嘔吐も併発している場
- 3.3.血便もしている場合
- 3.4.子犬の場合
- 3.5.老犬の場合
- 4.犬が下痢をしたときの食事や生活について
- 4.1.食事や水は少量ずつ回数を増やして与える
- 4.2.ひどい場合は絶食/絶水
- 4.3.自宅で安静にする
- 4.4.病院の受診を検討する
- 5.犬が下痢をしたときに病院に行くべき症状
- 6.犬の下痢に関するQ&A
- 6.1.Q.犬が下痢をしたらどうすればいい?
- 6.2.Q.犬が下痢をしているときの散歩はどうする?
- 6.3.Q.犬の下痢は何日続くと危険?
- 6.4.Q.下痢をしがちな犬におすすめの食事は?
- 6.5.Q.下痢で受診する際は何が必要?
- 7.犬が下痢をしたら獣医師にオンライン相談をしよう
- 8.犬の下痢の原因に合わせて対処しよう
犬が下痢する原因とは?

犬が下痢をする原因は、食事やストレスなどさまざまな原因が考えられます。
まずは、それぞれの下痢の原因について理解を深めていきましょう。
食事が原因の下痢
犬は食べ慣れていない食事や、食物アレルギーなどの食材によって下痢をする場合があります。新しいドッグフードや食べ慣れていない食材は、胃腸を刺激する場合があり、下痢をしてしまうケースが少なくありません。
食べ慣れていないものや、初めて食べる食材は、便や体調の様子を見ながら少量ずつ与えるのがポイント。
フードの切り替えの際は、元々食べていたドッグフードから徐々に量を切り替えましょう。
初めは4分の1程度、2~3日したら3分の1、4分の3と徐々に新しいドッグフードの量を増やし、10日程かけて新しいドッグフードに切り替えるのがコツです。
また、新しいものを食べて下痢をした際は、食物アレルギーの可能性も考えられます。少量ずつ与えて、症状が改善しなければ動物病院を受診するのがよいでしょう。
誤飲/誤食が原因の下痢
犬は、誤飲や誤食が原因で下痢になることもあるため注意しましょう。家の中や散歩中の拾い食いによって、誤って食べてはいけないものを食べると下痢の原因となる場合があります。
嘔吐を伴うことが多く、誤飲や誤食の可能性がある場合は、緊急な処置が必要になる場合もあるため、早めに動物病院に受診しましょう。
ストレスが原因の下痢
犬は、環境の変化や運動不足などのストレスによって下痢をするケースがあります。犬がストレスを感じる原因は、以下のような例が挙げられるのでチェックしてみましょう。
- 引っ越しによる環境の変化
- 長時間の留守番や来客
- 散歩や遊び時間が少ないことによる運動不足
- 新しい犬や子どもなど家族が増えた
- 犬が過ごすケージやトイレが清潔でない
犬がストレスを感じると、下痢以外にも食欲が低下したり、手足や尻尾などを噛んだりなどの行動が見られる場合もあります。
下痢の原因がストレスだと考えられる場合は、生活環境を改善したり、散歩時間や遊び時間を長くしたりして、ストレスの解消を心がけましょう。
感染症が原因の下痢
犬は、感染症が原因で下痢を起こすことがあります。下痢を引き起こす可能性のある感染症や菌は、以下の通りです。
- 犬パルボウイルス感染症
- 犬ジステンパーウイルス感染症
- 細菌性腸炎
- 大腸菌
- サルモレラ菌
犬の感染症による下痢の症状は、突然の下痢、血便、粘膜便や嘔吐などの症状が見られます。犬パルボウイルス感染症や犬ジステンパーウイルス感染症はワクチン接種、サルモレラ菌は生肉を避けることで予防も可能です。
寄生虫が原因の下痢
犬の下痢は、寄生虫が原因の場合もあるので注意しましょう。下痢を引き起こす可能性のある寄生虫は以下の通りです。
- 犬回虫
- コクシジウム
- ジアルジア
- クリプトスポリジウム
寄生虫による下痢の症状は、子犬に多く見られるのも特徴。犬回虫は母犬から子犬に感染(※)するケースもあり、虫体の成長に伴い、下痢や嘔吐などの症状が出てくる可能性があります。
糞便の顕微鏡検査で寄生虫の有無を確認できるため、早めに動物病院で診てもらうのがよいでしょう。
下痢の形状もチェック

犬の下痢には、泥状からゼリー状、水っぽいものまで形状はさまざま。事前に把握しておくと、獣医師の診断の際にも役立つので、ぜひチェックしておきましょう。
下痢の種類 |
特徴 |
軽度軟便 |
手で掴むことができるくらいの形がある便 |
重度軟便(泥状) |
泥状の軟便で、掴むことができない状態 |
水下痢 |
液状の軟便 |
血便(鮮血) |
鮮血が混じった便は、大腸や直腸などお尻に近い場所で出血が起きた際に見られる便 |
血便(黒っぽい) |
黒っぽい血便は、胃や十二指腸など上部の消化器で出血が起きた際に見られる |
粘膜便(ゼリー状) |
大腸性の下痢の際に見られるゼリー状やジャム状の |
白色便 |
胆のうや膵臓の消化不良の際に見られる白っぽい便 |
犬の下痢の対処法とは?

犬の下痢の対処法は、状況や年齢によって変わります。ここからは、それぞれの対処法を紹介するので、愛犬が下痢の際にどうすればいいか迷っている飼い主さんは参考にしてみてください。
元気で食欲ありの場合
犬が下痢をしている場合でも、元気で食欲がある場合は2~3日様子を見ましょう。ただし、水下痢や血便、白色便などの症状の際は、元気で食欲があっても早めの受診をおすすめします。
まずは半日程度絶食し、嘔吐がない場合は少量ずつ水を飲ませて脱水症状にも注意しましょう。1日に何回も下痢を繰り返すようなら、動物病院で検査してもらうのがおすすめです。
嘔吐も併発している場
犬が下痢の症状のほかに、嘔吐も併発している場合は、感染症や中毒などの可能性があるため、早めに動物病院を受診するのがよいでしょう。嘔吐物や便をビニール袋や容器に包んで病院に持っていくと、診断や検査がしやすくなります。
また、便や嘔吐物は時間が経つと変色するため、下痢や嘔吐をした後は写真を撮影しておくとよいでしょう。
血便もしている場合
犬が血便もしている場合は、胃腸炎や食道、胃、十二指腸などの腫瘍、寄生虫などさまざまな病気の可能性があるので、早めに動物病院で診てもらいましょう。血便はどこからか出血しているため、緊急性が高い場合もあります。
血便の下痢が出た際も同様に、便や嘔吐物の現物を持参するか、難しい場合には写真を撮影しておきましょう。
子犬の場合
子犬は免疫力が低く下痢を起こしやすいので、元気がある場合は3日程度様子を見ましょう。新しい環境でのストレスや、新しいフードに慣れていないとよく下痢を起こしやすくなります。
ただし、3日以上続く場合は、脱水症状を起こす可能性があるため、動物病院の受診がおすすめです。動物病院では、下痢止めの処方や適切なアドバイスをしてもらえる可能性があるので、心配な方は早めに受診するようにしましょう。
老犬の場合
老犬は、加齢によって消化器官が衰えたり、体温調節機能が低下したりするため、下痢をしやすくなります。そのため、こまめな水分補給で脱水症状に気を付けつつ、胃腸に負担をかけない食事に切り替えるのがおすすめです。
例えば、シニア専用の消化によいドッグフード、ウェットフードなどのやわらかい食事がおすすめです。ドライフードはぬるま湯でふやかすことで、老犬でも食べやすくなり、適度に水分補給ができます。
ただし、食事を切り替えても改善しない場合や、元気がない、嘔吐や血便などほかに症状がある場合は、すぐに病院を受診するようにしましょう。
犬が下痢をしたときの食事や生活について

食事や水は少量ずつ回数を増やして与える
犬が下痢をしたときは、消化しやすい食事や水を少量ずつ回数を増やして与えるようにしましょう。普段食べているドライフードを与える場合は、ぬるま湯でふやかしてやわらかくするのがおすすめ。
また、少量で消化されやすいタンパク源は、ささみや鶏むね肉、白身魚などを加熱したものです。食物繊維が豊富なさつまいもやかぼちゃ、キャベツ、キノコ類を一緒に与えるのもおすすめです。
ひどい場合は絶食/絶水
犬の下痢がひどい場合には、半日~1日程度絶食、絶水するのが望ましいです。胃腸を休めてあげることで、症状が改善する可能性があります。
下痢のときは「水分補給が必要なのでは?」と疑問に思う方も多いと思いますが、下痢を繰り返すことでさらに脱水となる可能性もあります。下痢がひどい場合は、速やかに病院に受診し獣医師の診断を受けるのがおすすめです。
ただし、子犬や老犬、持病がある場合は絶食、絶水が危険な状況もあります。そのため、子犬や老犬の場合は絶食、絶水はせず、消化によいものを少量ずつ与えて、様子を見るのがよいでしょう。
自宅で安静にする
犬が下痢をしている場合は、なるべく自宅で安静にするのがよいでしょう。ドッグランやトリミング、シャンプー、慣れない場所への外出などはストレスとなる場合があるため、控えておきましょう。
また、犬の散歩はその日はお休みするか、いつもより歩く距離を少なくするのがおすすめ。散歩に行かないことがストレスとなるようなら、愛犬の様子を見守りつつ、ゆっくり散歩へ行くのもよいでしょう。
病院の受診を検討する
愛犬の下痢が病気の可能性が高い場合には、早めに動物病院への受診を検討するのがおすすめです。例えば元気があり、新しいドッグフードに切り替えたり、環境が変わったりとストレスや消化不良が下痢の原因と考えられる場合は、2~3日程度自宅で様子を見てもよいでしょう。
しかし、思い当たる節がない場合は、感染症や寄生虫などの病気の可能性が考えられます。
早めに獣医師に診てもらうことで、愛犬を痛みや辛さから開放してあげることにも繋がるので、判断に迷ったときは早めに獣医師に相談しましょう。
犬が下痢をしたときに病院に行くべき症状

愛犬が下痢をした際、病院に連れて行った方がいいのか、自宅で様子を見てもいいのか判断が難しい場合も多いです。ここでは、犬が下痢をしたときに病院に行くべき症状について紹介するので、病院に行くかどうかの判断に役立ててください。
- 水下痢や血便が出ている場合
- 下痢を何度も繰り返す場合
- 元気があっても下痢が3日以上続く場合
- 下痢だけでなく、嘔吐が併発している場合
- 下痢だけでなく、元気がない、食欲なしの場合
犬の下痢に関するQ&A

ここからは、犬の下痢に関する質問と回答を紹介します。
Q.犬が下痢をしたらどうすればいい?
愛犬が元気で食欲がある場合には、2~3日程度様子を見てもよいでしょう。なるべく食事は消化のよいものを少量ずつ与え、水分もこまめに与えてください。
ただし、血便や水下痢、そのほかに症状がある場合は、速やかに動物病院を受診するのがおすすめです。元気や食欲がある場合でも、3日程度経っても下痢の症状が改善しない場合は病院で検査を受けましょう。
Q.犬が下痢をしているときの散歩はどうする?
犬が下痢をしている場合の散歩は、その日はお休みするか、いつもより歩く距離を少なくするのがおすすめ。ただし、元気があり、散歩に行かないことがストレスとなるようなら、愛犬の様子をみながらゆっくり散歩するのもよいでしょう。
Q.犬の下痢は何日続くと危険?
犬の下痢が3日以上続くと病気の可能性が考えられるので、早めに獣医師に相談することをおすすめします。
元気がない、嘔吐もしている、血便や白色便がでているなど、そのほかの症状がある場合も病気の可能性も高くなるため、早めの受診をすることが大切です。
Q.下痢をしがちな犬におすすめの食事は?
下痢をしがちな犬には、少量で消化されやすいとされるタンパク源のささみや鶏むね肉、白身魚などを加熱したものがおすすめ。整腸作用のある食物繊維(※)が豊富なさつまいもやかぼちゃ、キャベツ、キノコ類を一緒に与えるのもよいでしょう。
※“ROYAL CANIN 情報”参照
Q.下痢で受診する際は何が必要?
愛犬の下痢で動物病院を受診する際は、以下のものを持参しましょう。
- 診察券や保険証
- ビニール袋や容器に入れた排泄物
- 排泄物の写真
- エチケット袋やティッシュ
犬が下痢をしたときは、排泄物の写真や現物を持っていくと診断に役立ちます。排泄物や嘔吐物は時間が経つと色が変わってしまったりするため、排泄直後の写真を残しておくと獣医師も診断がしやすくなります。
また「いつから症状があるのか」「下痢の頻度」「ほかの症状はないか」「元気や食欲があるか」などについても応えられるように準備しておきましょう。
犬が下痢をしたら獣医師にオンライン相談をしよう
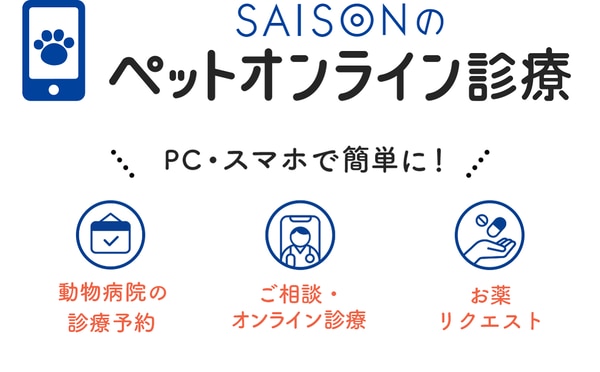
SAISONのペットオンライン診療は、獣医師にオンライン相談できるサービス。犬の下痢や嘔吐など気になる症状のお悩み相談にも対応しており「動物行動学」の観点から、なぜそのような行動をとるのか要因を分析して、改善に取り組む診療方法を提案します。
【以下のようなお悩みに対応】
・犬が下痢をした
・ほかにも気になる症状がある
・元気はあるけど病院に連れていくべき?
・最近頻繁に下痢をしやすい
・うんちがゆるいけど食事を改善した方がいい?
まずは、愛犬がどのような状態なのかしっかりカウンセリングを行い、プランを一緒に検討できるのもポイント。
動物病院へ通院するかをオンラインで事前に判断してもらえるので、犬にストレスもかけずに診察を受けることが可能です。
また、オンライン相談ではお薬も処方できるのが特徴で、郵送または来院で薬の受け取りも可能です。
※オンライン診療には、システム利用料280円(税込)が利用都度かかります。会員登録料は無料です。
犬の下痢の原因に合わせて対処しよう

犬の下痢は、ストレスや消化不良などからくるものや、感染症や寄生虫など病気からくるものなどさまざまな原因が考えられます。
元気や食欲がある場合は2~3日程度様子を見る選択肢もありますが、便の形状やそのほかの症状によっては早めに獣医師に診てもらった方がよいでしょう。
本記事で紹介した犬の下痢の原因や、対処法を参考に、愛犬の症状に合った対処をしてあげてください。
また、病院受診の判断や、対処法に迷ったら、オンライン診療サービスを利用して医師に指示を仰いでもらいましょう。

