
【犬のしつけ】覚えておきたい基本の一覧と注意点やポイントも紹介
「犬のしつけ方が分からない」「しつけがうまくいかない」という方は必見!本記事では、基本の犬のしつけ方の一覧、合図やポイント、しつける際の注意点について紹介します。
また「犬のしつけはいつから?」「順番はある?」といった初心者によくある疑問についても解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
目次[非表示]
- 1.犬のしつけは必要
- 2.【犬の基本のしつけ一覧】ポイントと合図も解説
- 3.犬をしつける際の注意点
- 3.1.家族でしつけを統一する
- 3.2.叱ったり暴力をふるったりしない
- 3.3.できたら褒めてあげる
- 3.4.しつけ教室や預かり訓練も検討する
- 3.5.犬のしつけ用首輪やスプレーなどのグッズを活用する
- 4.【Q&A】犬のしつけに関する疑問を解消!
- 4.1.Q.子犬のしつけはいつから?
- 4.2.Q.犬のしつけに順番はある?
- 4.3.Q.何歳まで犬のしつけは可能?
- 4.4.Q.犬のしつけはいつまでに行うべき?
- 5.犬のしつけがうまくいかない場合はプロにオンライン相談してみよう
- 6.愛犬のためにもしつけはしっかり行おう
犬のしつけは必要

犬のしつけは、犬と人が快適に生活するために必要です。愛犬をきちんとコントロールしてあげることで、周囲に迷惑をかけたり、事故やケガなどのリスクから守ってあげたりすることができます。
しつけをせずに育ってしまうと、周囲の人に噛みついたり、鳴き声で近所迷惑になったりする場合もあります。愛犬が生きやすい生活を作るためにも、しっかりとしつけを行いましょう。
【犬の基本のしつけ一覧】ポイントと合図も解説

犬の基本のしつけ方を紹介します。しつける際のポイントや合図についても解説するので、ぜひ参考にしつけを行ってみてください。
トイレ
トイレのしつけは、愛犬を迎えたその日から始めましょう。トイレトレーニングには、トイレトレー、トイレシート、おやつが必要です。
- トイレの環境を整える
- 愛犬の様子を観察する
- トイレサインを確認したら、トイレの上に誘導する
- 「トイレ、トイレ」と声かけを行う
- トイレが成功したらすぐに「いい子!」と声かけをして褒めておやつをあげる
トイレサインとは、愛犬がトイレをする前にしぐさ。一般的には、床の匂いをクンクンかいだり、そわそわしたり、その場でくるくると回ったりする子が多いです。トイレトレーニング中は、愛犬の様子をしっかりと観察し、トイレのタイミングできちんと誘導してあげることがポイント。
トイレサインがよく分からない飼い主さんは、2時間おきにトイレの上まで連れてってあげましょう。おもちゃやおやつを使ってトイレまで誘導したり、抱っこしてトイレに連れて行ってあげたりする方法でOK。
合図や掛け声は何でもよいですが、2回目以降は愛犬を混乱させないように統一してあげるのがポイントです。
噛み癖・甘噛み
噛み癖や甘噛みのしつけは、噛んでよいものと悪いものを明確にすることが大切。とくに子犬は好奇心や遊びの延長線で、甘噛みすることがよくあります。しかし、甘噛みを許してしまうとエスカレートして本気噛みに発展するケースもあるため、しつけておくことが重要です。
人の手を噛むケース
- 噛んだら「痛い!」や「ダメ!」などといってその場を離れる
- その場から飼い主さんが立ち去る
- 10秒くらいで元に戻る
人を噛むケースは「噛んではいけない」ということをきちんと教えてあげることがポイント。
愛犬にとって飼い主さんは大好きな存在なので、噛んだら大好きな飼い主さんがいなくなってしまうということを学習させます。ただし、離れる時間が長いと要求吠えに発展するケースがあるため、愛犬から離れる時間は10秒程度が望ましいです。
物や家具などを噛むケース
- 噛んだら「ダメ」や「ノー」などの指示を出す
- 「オスワリ」や「マテ」などの指示を出す
- できたらご褒美のおやつをあげる
ものや家具などを噛んでしまう場合は「ダメ」「ノー」などの合図を出し、違うコマンドによって噛んでいるものを離させるのがポイント。ただし、ものを噛む破壊行動は、運動量が足りていなかったり、ストレスが溜まっていたりするケースもあります。
ガムやおもちゃなど、噛んでもいいものを用意したり、遊びで運動不足を解消してあげたりすることも、噛み癖を直す1つの手段です。
無駄吠え
人に吠えたり、インターホンに吠えたりする場合は、音や人に慣れさせてあげることがポイントです。吠えるという行為は、警戒心や恐怖心からきている場合が多いため、対象のものに慣れさせてあげることで吠えるリスクを軽減できます。
無駄吠えのしつけ方は、インターホンや人などいつも吠えるものに対して、吠えなくなったときにおやつをあげるようにします。最初のうちは、人を見ただけでご褒美を与えて「人が来たらいいことがある」と教える方法も有効でしょう。
とくに生後3週間から16週目は社会化期と呼ばれており、音や人などさまざまなものを受け入れやすい時期です。この時期に人や音、触られるなどといったことに慣れさせておくと、あらゆる問題行動を防げるでしょう。
おすわり
おすわりのしつけは一見必要ないように思いますが、さまざまな問題行動を抑制するコマンドとして役立ちます。おすわりは、体を落とした体制になるため、犬が落ち着いた状態になるといわれています。そのため、なるべく早めに習得しておくと、さまざまなしつけがしやすくなるのでおすすめです。
- 犬の鼻先におやつをもっていく
- おやつを頭の上に移動し、愛犬が上を向いた際に腰を落とすように誘導する
- 腰が下がらない場合は、お尻をやさしく押して座らせる
- おすわりの姿勢になったら「おすわり」と声をかける
- できたら「いい子」「よし」などと声掛けし、すぐにおやつをあげる
上記の状態でおすわりができるようになったら「おすわり」と合図をし、おすわりができるように練習しましょう。おやつをもっている手に飛びつくといった場合は、犬が届かないくらいの高い距離に手を上げて行ってみてください。
散歩
散歩のしつけは、飼い主さん主導のリーダーウォークです。散歩中に愛犬が途中で立ち止まって動かなくなったり、行きたい方向に引っ張ったり、他の犬に吠えたりということが少なくなります。
犬が好き勝手に動けるように散歩してしまうと、事故やケガの危険性もあるため、愛犬をしっかり制御できる状態にしましょう。
- おやつを片手に持つ
- 飼い主さんの横を歩かせる
- 飼い主さんの前を歩いたら立ち止まる
- うまく歩けているときに「いい子」「よし」などとアイコントをし、おやつをあげる
リーダーウォークでは、常にリードが緩んだ状態を保ちます。最初はなかなか前に進むことができませんが、根気よく行いましょう。
散歩中の他の犬に吠えたり、引っ張ったりすることがあれば、立ち止まったり、Uターンしたりするのも効果的です。
散歩のトレーニングの際も「いい子にできたらご褒美がもらえる」ということを学習させることが大切です。
車の音や人、他の犬の刺激に慣れない場合は、頻繁に触れる機会を作り、慣れさせることもしつけの1つ。積極的に散歩に出かけて、さまざまなものに慣れされる練習をしましょう。
ハウス
ハウスのしつけは、愛犬がおとなしくお留守番できるようになったり、災害時に避難したりするときに役立つので早めにしつけておくのがおすすめ。室内で放し飼いにして飼う予定の方でも、愛犬が安心できる場所が必要なので愛犬の大きさに適したゲージを用意してあげましょう。
- 「ハウス」とい合図を出し、おもちゃやおやつを使ってハウスに誘導する
- 愛犬がハウスに入ったらおやつをあげる
- ハウスの中にいる間におやつを与える
- 「ハウス」と声かけをしてハウスに入るようになったら「いい子!」と声をかけおやつをあげる
- 扉を閉めた状態にして、おやつをあげる
ハウスもほかのしつけと同様に、ハウスの中に入ったらいいことがあると学習させる方法です。クレートに入るしつけの際も同様の方法でしつけできます。
扉を閉めた際に閉じ込められたと認識しないように、扉を閉めていた状態でも同じ訓練を行うようにしましょう。
食事
食事のしつけは、きちんと食べさせる愛犬の健康を守るために大切。おやつばかり与えたり人間の食べるものを与えたりすると、ドッグフードを食べなくなるため注意が必要です。
また、初めのうちはフードやおやつを手から与えたり、食事中にフードをさわったりして、飼い主さんがフードに触っても威嚇されないように慣れさせるのもポイント。
- フードの入った食器を手に持ち、おすわりさせる
- フードを前に出して「まて」と指示を出す
- 10秒ほどまてたら「よし」と合図を出す
また、飼い主さんが食事をしている際に、愛犬におやつを与えたり、人間の食べ物を与えたりするのはやめましょう。かわいい眼差しで見つめられるとおやつをあげたくなりますが、食事中に要求してきたり、テーブルの上のものを食べてしまったりと問題行動に繋がる場合があります。
アイコンタクト
アイコンタクトは、犬と飼い主さんが信頼関係を築けている証拠です。アイコンタクトができれば、飼い主さんに意識を集中でき、コミュニケーションがとりやすくなります。
- 飼い主さんを見たらおやつをあげる
- 愛犬の名前を呼び、飼い主さんを見たらおやつをあげる
上記を繰り返し行うことで、愛犬が常に飼い主さんを気にするようになります。おすわりやふせ、まてなどのコマンド、さらには散歩中の引っ張り行動もコントロールできるようになるので、愛犬を突発的なトラブルから守るためにもぜひ覚えさせておきましょう。
音に慣れさせる
音に慣れさせるしつけは、無駄吠えや散歩中の引っ張り行動などの問題行動のリスクを軽減できます。
犬は、人間と同様に初めて聞く音に恐怖心や警戒心を抱くため、音の刺激によって自分を守るために吠えたり引っ張ったりすることがあります。
そのため、音にびっくりして逃げてしまったり、警戒して吠えたりする場合は、車の音、窓を開ける音、工場の音など、さまざまな音に慣れさせてあげましょう。
とくに子犬の場合は生後3週間~16週目の社会化期は、刺激を受け入れやすい時期。散歩デビューがまだの場合でも、抱っこして散歩をしたり、窓を開けたりしてさまざまな音に慣れさせてあげましょう。
人に慣れさせる
人に慣れさせるしつけも、噛む・吠えるといった問題行動のリスクを減らせます。例えば、来客時に必要以上に吠えたり、飼い主以外の人が触ろうとしたら噛みついたりといったケース。
まずは飼い主さんからスキンシップを通して、手、頭、お尻、足、爪などさまざまな部分を触れられることに慣れさせましょう。
次に、飼い主さん以外の人とたくさん顔を合わせるようにさせます。飼い主さん以外の人が犬に触れる場合は、まずは手の匂いからかがせて犬の方から近づいてくるのを待ちましょう。慣れてきたら徐々に触れる場所を増やしていきます。
とくに足先や口周りといった部分は犬が触られるのを嫌がる傾向にあるため、徐々に触る範囲を広めるのがおすすめです。人の緊張や恐怖心は愛犬に伝わる場合があるので、リラックスした状態でやさしく声をかけながら行いましょう。
犬をしつける際の注意点

犬をしつける際は、注意するべきポイントがあります。「しつけがうまくいかない」という方は、注意点で当てはまるものがないか確認してみましょう。
家族でしつけを統一する
犬をしつける際は、家族でしつけを統一することが大切です。合図や対応が家族で変わってしまうと、愛犬が混乱してしまいます。
「ダメ」「ノー」などの合図だけではなく、名前を呼ぶときの同じ呼び方が望ましいです。表情や声のトーンなども指示によって分かりやすくしてあげると、愛犬も指示を理解しやすくなります。
叱ったり暴力をふるったりしない
愛犬のしつけがうまくいかない場合でも、絶対に叱ったり暴力をふるったりするのはやめましょう。怒られたことに対しての恐怖心によって、さらにしつけがうまくいかないケースもあります。
いけないことをしたときは「ダメ」や「ノー」などといい、飼い主が愛犬から離れるというしつけ方法があります。
愛犬は大好き飼い主さんがいなくなってしまうことで「いけないことをしたら楽しい時間が終わってしまう」ということを学習します。ただし、この離れる時間が長すぎると、要求吠えをしてしまう恐れもあるため、10秒程度と短い時間で戻るようにしましょう。
できたら褒めてあげる
犬のしつけのすべてに共通することですが、できたら褒めてあげることがとても重要です。犬がしつけを覚えてくれるのは「できたらいいことがある」と学習するとき。
悪いことを叱るのではなく、いいことができたときにタイミングよく褒めて「できたらいいことがある」と気づかせてあげることがポイントです。
しつけ教室や預かり訓練も検討する
しつけ一覧で紹介したやり方がうまくいかない場合には、しつけ教室や預かり教室も検討しましょう。
しつけ教室とは、ドッグトレーナーや獣医師などのプロに犬のしつけ方法を学び、実際にしつけを実践する教室です。飼い主が一緒に教室に行ってレッスンを受けるタイプや、愛犬だけを預ける保育園、幼稚園型タイプ、しっかり学べる預かり訓練タイプなどさまざまな種類のしつけ教室があります。
犬のしつけ用首輪やスプレーなどのグッズを活用する
噛み癖や無駄吠えなど問題行動がなかなか直らないという場合には、犬のしつけ用首輪やスプレーなどのグッズを活用するのもおすすめです。
しつけ用首輪は、ひっぱり癖を防止するものや、無駄吠えを防止するものなどさまざまなグッズが販売されています。
しつけ用スプレーは、噛み癖を直すための苦い味がするものや、トイレのしつけスプレーなどがあります。犬のしつけに苦戦した際は、こうした便利アイテムも活用しましょう。
【Q&A】犬のしつけに関する疑問を解消!

ここからは、犬のしつけに関するよくある質問と回答を紹介します。
Q.子犬のしつけはいつから?
子犬のしつけは、生後2~3ヶ月頃から行うのがおすすめ。生後3週間~16週目の社会化期と呼ばれる時期で、あらゆる物事やルールを受け入れやすい時期となっています。
生後2ヶ月頃まではまだ小さいので、お母さんや兄弟たちの中でコミュニケーションの取り方を学び、その後音や人などさまざまなものに徐々に慣れさせていきましょう。
また、子犬の方がさまざまなものを短期間で受け入れる傾向にありますが、成犬になってもしつけは可能です。ただし、成犬になるとこれまでの生活で癖がついている可能性もあるため、なるべく早い段階からしつけてあげることが大切です。
Q.犬のしつけに順番はある?
子犬のしつけに順番はありませんが、以下の順番で覚えさせるのがおすすめです。
- 名前を教える
- トイレトレーニング
- アイコンタクト
- おすわり
- 食事
- 人に慣れさせる
- ハウス
- 音に慣れさせる
- 噛み癖、甘噛み
- 散歩
名前やアイコンタントやおすわりを覚えると、さまざまなしつけに応用できます。ただし、順番や覚える時期などは個体差があるため、愛犬の様子を見ながらペースを合わせてあげてください。
Q.何歳まで犬のしつけは可能?
犬のしつけは、何歳でもしつけが可能です。しかし、成犬になるにつれて時間がかかる傾向にあるので、子犬のうちからしつけを行っておいた方がよいでしょう。
Q.犬のしつけはいつまでに行うべき?
犬のしつけは、いつまでに行うといった期限はありません。犬は年を取るにつれてしつけに時間がかかる場合があるため、根気よくしつけることが大切です。
ただし、子犬のうちは環境への適用能力が高く、興味によってさまざまな物事やルールを吸収できます。可能であれば子犬のうちからしつけするのが、しつけも楽にできそうです。
犬のしつけがうまくいかない場合はプロにオンライン相談してみよう
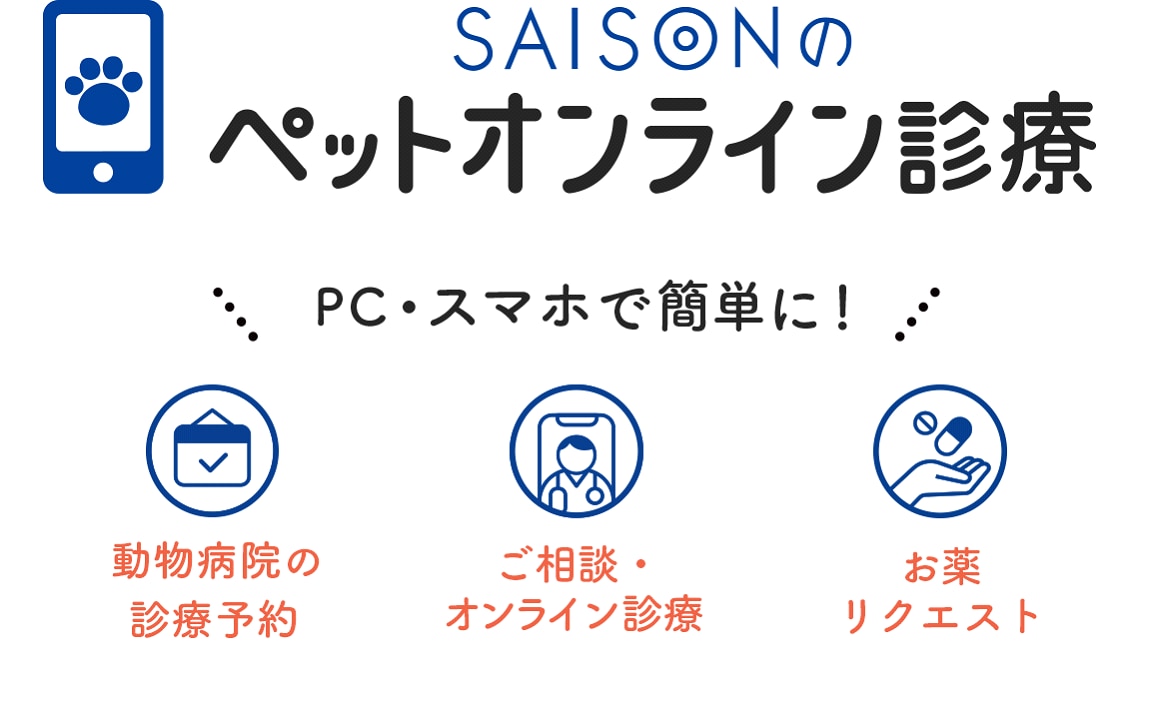
SAISONのペットオンライン診療は、獣医師にオンライン相談できるサービス。愛犬の問題行動やしつけのお悩み相談にも対応しており「動物行動学」の観点から、なぜそのような行動をとるのか要因を分析して、改善に取り組む診療方法を提案します。
【以下のようなお悩みに対応】
・飼い主、他人に吠える、泣き止まない
・散歩中歩かない、リードを引っ張る
・噛みつく癖がある、体を触らせてくれない
・ご飯を食べない、拾い食いをする
まずは、カウンセリングで愛犬がどのような状態なのかしっかりカウンセリングを行い、プランを一緒に検討できるのもポイント。動物病院へ通院する必要がないので、愛犬にストレスもかけずに診察を受けることが可能です。
※オンライン診療には、システム利用料280円(税込)が利用都度かかります。会員登録料は無料です。
愛犬のためにもしつけはしっかり行おう

犬のしつけは、犬が社会のなかで安全に生活していくために必要なものです。飼い主さんと愛犬の信頼関係を築くことで、お互い快適な生活が送れます。
しかし、しつけ方法を間違えてしまうと恐怖心を与えたり、怪我や事故の原因になったりするケースもあります。
しつけがうまくいかない場合は、獣医師やドッグトレーナーなどプロにサポートしてもらい、しっかりとしつけを行いましょう。

